ChatGPT学習モードを使うときの注意点と、賢い活かし方
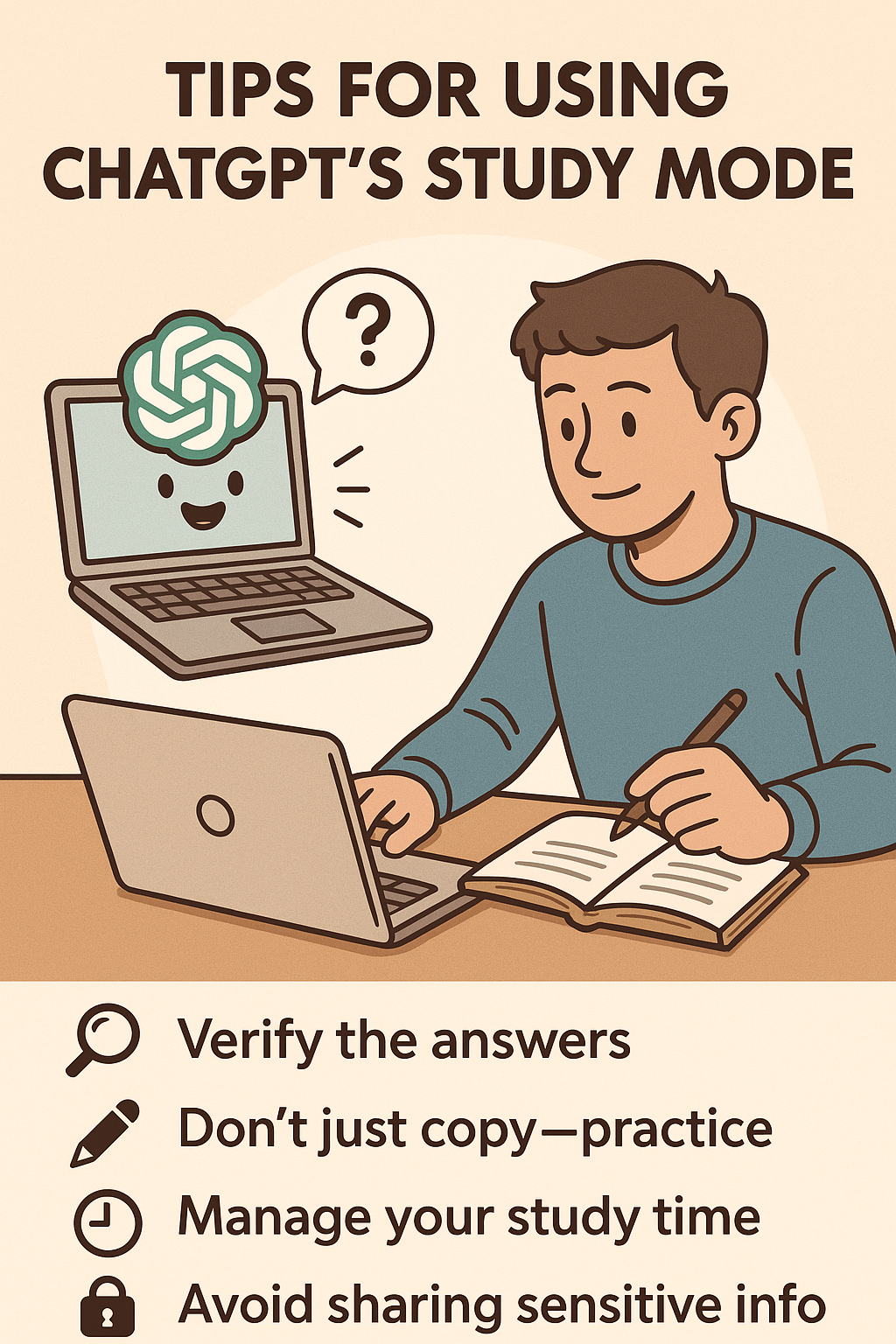
前回の記事では、ChatGPTの学習モードを実際に使ってみて、
家庭教師の僕が「震えた」体験を書きました。
簿記の仕訳を無限にキャッチボールしながら覚えていく感覚――
これは本当に革命的でした。でも、実際に数時間だけどずっと使ってみて、
「便利だけど気をつけないと危ないな…」
と感じるポイントもはっきり見えてきました。
今回は、家庭教師の立場から見た 学習モードの注意点と活かし方 を整理します。
◎ 便利さの裏にある落とし穴
AI学習モードは本当に優秀です。
でも、使い方を間違えると 「分かった気になるだけ」 で終わる可能性があります。
僕が実際に感じた落とし穴はこの4つ。
◆ 1. AIの答えを鵜呑みにしない
AIはときどき平然と間違えます。
簿記の仕訳でも、勘定科目を微妙に間違えたり、数字を逆にしたりすることがあります。
例:「現金過不足の処理で最終的に雑損失になるはずが、雑収入で回答してきた」
一瞬「え、そうだっけ?」と混乱します。
だから、最終確認は必ずテキストや過去問で。
◆ 2. 受け身学習に陥る
質問すれば即答が返ってくる環境は、めちゃくちゃ快適です。
でも、人は快適すぎると 手を動かさなくなる んですよね。
僕も最初の1日目はこうなりました。
「あ、なるほどね〜」で終わって、ノートには何も書いてない(笑)
この状態だと、次の日にはもう半分忘れています。
やっぱり 自分の手でアウトプットする時間 は絶対に必要です。
◆ 3. 学習のペースは自分で管理するしかない
AIは質問には答えてくれますが、
「今日はここまでやろう」
「この単元はあと1日で仕上げよう」
という 進捗管理はしてくれません。
人間の先生なら「そろそろ次に行こう」と区切ってくれますが、
AIは無限に付き合ってくれるので、気づくと1時間同じ問題で遊んでしまうことも…。
僕は手帳に「今日の学習テーマ」を書いてから学習モードを使うようにしました。
この一手間だけで、学習効率が全然違います。
◆ 4. 個人情報は絶対に入れない
学習モードは安全設計とはいえ、
本名や学校名、住所などは入力しない方が安心です。
特に家庭教師や塾の先生なら、
生徒の名前や答案はそのまま打ち込まない ルールを決めておくべきです。
僕は問題文を少し変えたり、名前を「Aくん」「Bさん」に置き換えて使っています。
◎ 賢く活かすコツ
上の注意点を押さえたうえで、
僕がやってみて「これ最強だな」と感じた活用法がこちらです。
◆ 1. 先に自分で解いてから質問する
最初からAIに頼ると、理解が浅くなります。
僕は「問題を解く→自分で答えを作る→AIに投げる」の順番にしています。
間違えたときだけ深掘りして質問するほうが、
記憶にしっかり残るのを実感しました。
◆ 2. キャッチボールを意識して使う
ただ答えを聞くだけではなく、
自分からも質問を返す ことで理解が深まります。
「じゃあ、もしこの勘定科目じゃなかったら何が起こる?」
「決算整理仕訳ではどうなる?」
こういうやり取りを自分で作ると、学習モードは本領を発揮します。
◆ 3. 学習の記録を残す
学習モードは便利ですが、会話は流れていってしまいます。
僕は「今日の学び」を一言だけでも手帳に残すようにしています。
◎ 今日覚えたこと:現金過不足は決算整理で雑損失or雑収入で処理
こうすることで、後から見返せるし、AI任せの受け身学習にならないんです。
◎ まとめ:AIは万能ではない。でも最強の相棒になれる
ChatGPT学習モードは、
「無限にキャッチボールできる家庭教師」を手に入れたような感覚です。
でも、万能ではありません。
◆ 答えの正誤は必ず自分で確認する
◆ 受け身にならず、必ずアウトプットする
◆ 学習計画と進捗は自分で管理する
◆ 個人情報は絶対に入力しない
この4つを守れば、AIは最強の学習相棒になります。
家庭教師としても、これを生徒に正しく使わせれば、
「AI+人間のハイブリッド学習」 で伸び率は間違いなく跳ね上がります。
僕はこの方法をもっと磨いて、
次は実際に生徒との授業にも組み込んでみようと思っています。
#家庭教師ブログ #AI学習 #ChatGPT学習モード #教育の未来 #学習効率UP #簿記学習