【シリーズ第2回】中学理科の図解ノート術|実験・模式図を武器にする方法
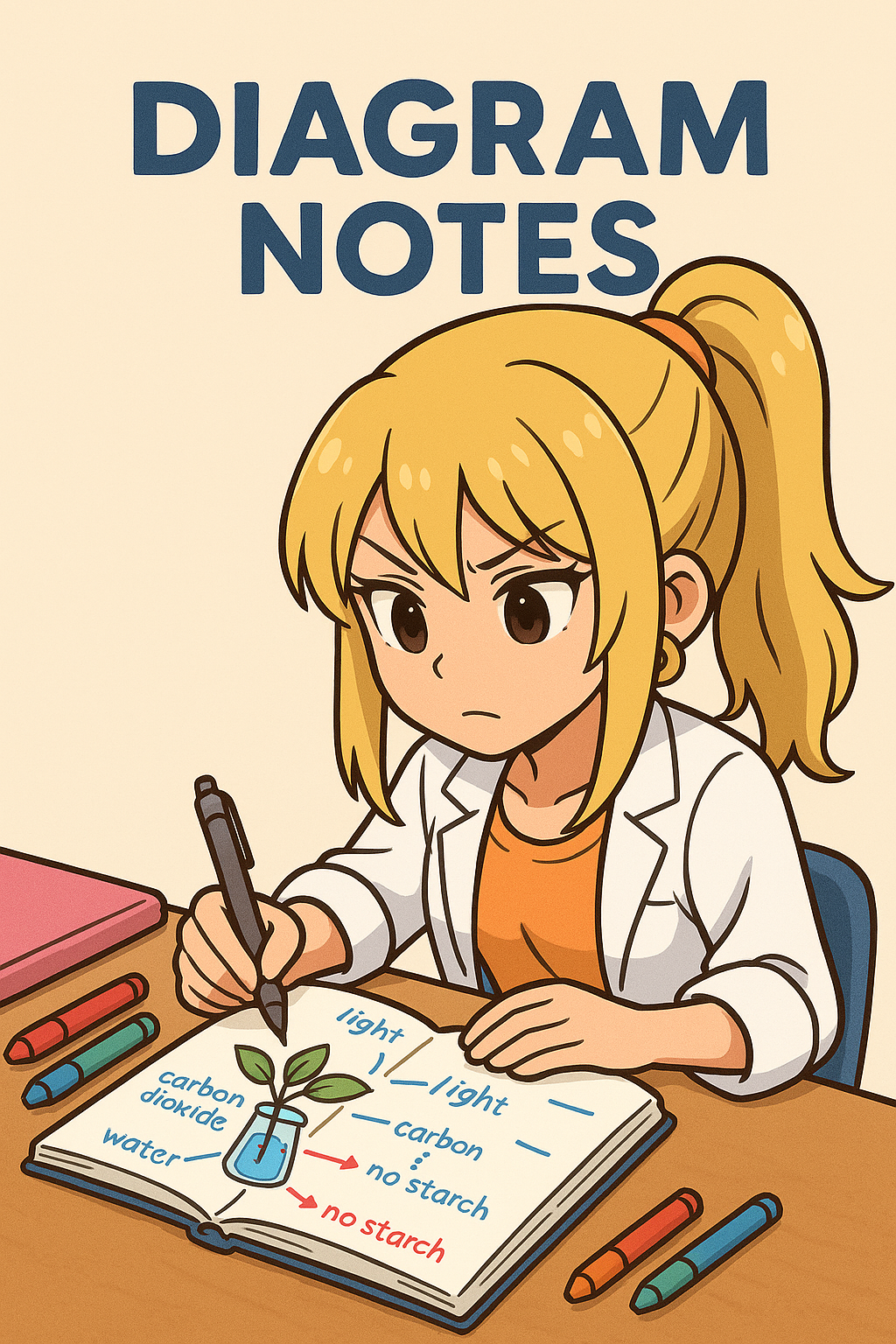
はじめに
理科は暗記科目だと思っている人が多いですが、実際には「図で理解する力」が得点を左右します。
特に中学理科では、実験の手順や条件、観察結果、模式図やグラフといった視覚的な情報が頻繁に出題されます。
文字だけで覚えようとすると混乱しやすく、条件と結果がごちゃ混ぜになりやすいものも、図解ノートにまとめれば一目で関係性がわかります。
理科の図解ノートが有効な理由
◎ 実験の手順や条件を整理しやすい
複雑な手順も図で描くことで、流れや全体像が理解しやすくなります。
◎ 結果や変化を視覚的にまとめられる
結果の違いを色や形で示すと、暗記しやすくなります。
◎ 条件と結果の因果関係を理解できる
条件を変えると結果がどう変わるかを矢印でつなぐことで、「なぜそうなるのか」が理解できます。
◎ 記憶に残りやすく、試験中にイメージしやすい
図を見た記憶がそのまま試験中に頭に浮かび、解答に直結します。
実験図のまとめ方
◎ 教科書や資料集の図を丸写しせず、重要な部分だけを簡略化して描く
細部まで完璧に描く必要はなく、試験に出やすい構造や器具を正確に押さえることが大事です。
◎ 条件と結果を色分けする
条件は青、結果は赤など役割を固定しておくと、見返したときに瞬時に区別できます。
◎ 器具の名前は省略せず書く
試験で器具名を問われることは多く、省略すると復習時に混乱します。
◎ 注意点や安全面は吹き出しで補足する
「火気厳禁」「加熱は弱火で」など、実験の注意はその場で図に入れると忘れにくくなります。
例:光合成の実験なら
◎ 条件:光の有無、二酸化炭素の有無、水の有無
◎ 結果:デンプンの生成、ヨウ素液での変色
◎ 図解:ビーカー、植物、覆いの有無をシンプルに描き、条件ごとの結果を並べる
模式図のまとめ方
◎ 流れや位置関係を強調する配置にする
血液の流れや天体の動きなどは、視線の流れを意識して配置します。
◎ 左から右、上から下へ自然に視線が動くように描く
情報の順番を間違えると、理解が逆転してしまいます。
◎ 重要語句は枠や色で目立たせる
用語を強調することで、キーワードの記憶が強まります。
◎ 数値や単位も必ず書く
音の速さ、電圧、距離など、単位まで含めて覚えるのが理科の得点アップのコツです。
例:天体の動きなら
◎ 太陽・地球・月の位置関係を模式化
◎ 公転・自転の矢印を入れる
◎ 公転周期や自転周期など数値も明記
色分けのポイント
◎ 赤は重要語句や結論
◎ 青は条件や設定
◎ 緑は例や補足説明
このルールを決めて統一することで、復習時に情報を瞬時に分類できます。
理科版 図解ノート作りの注意点
◎ 図が複雑になりすぎないようにする
テスト直前に見て一瞬で理解できるかどうかを基準にします。
◎ 実験の「なぜその条件にするのか」も必ず書く
条件だけ覚えても、理由を忘れると応用問題に対応できません。
◎ グラフや表は単位や目盛りまで正確に再現する
単位を間違えると正解にならない問題も多いため注意が必要です。
まとめ
理科は図やグラフを正しく使いこなすことで、得点力が大きく上がります。
図解ノートは写す作業ではなく、「自分が理解しやすい形に再構成する作業」です。
次回(第3回)は歴史編として、年表や因果関係を整理する図解法、人物や出来事をイラストで覚える方法を紹介します。