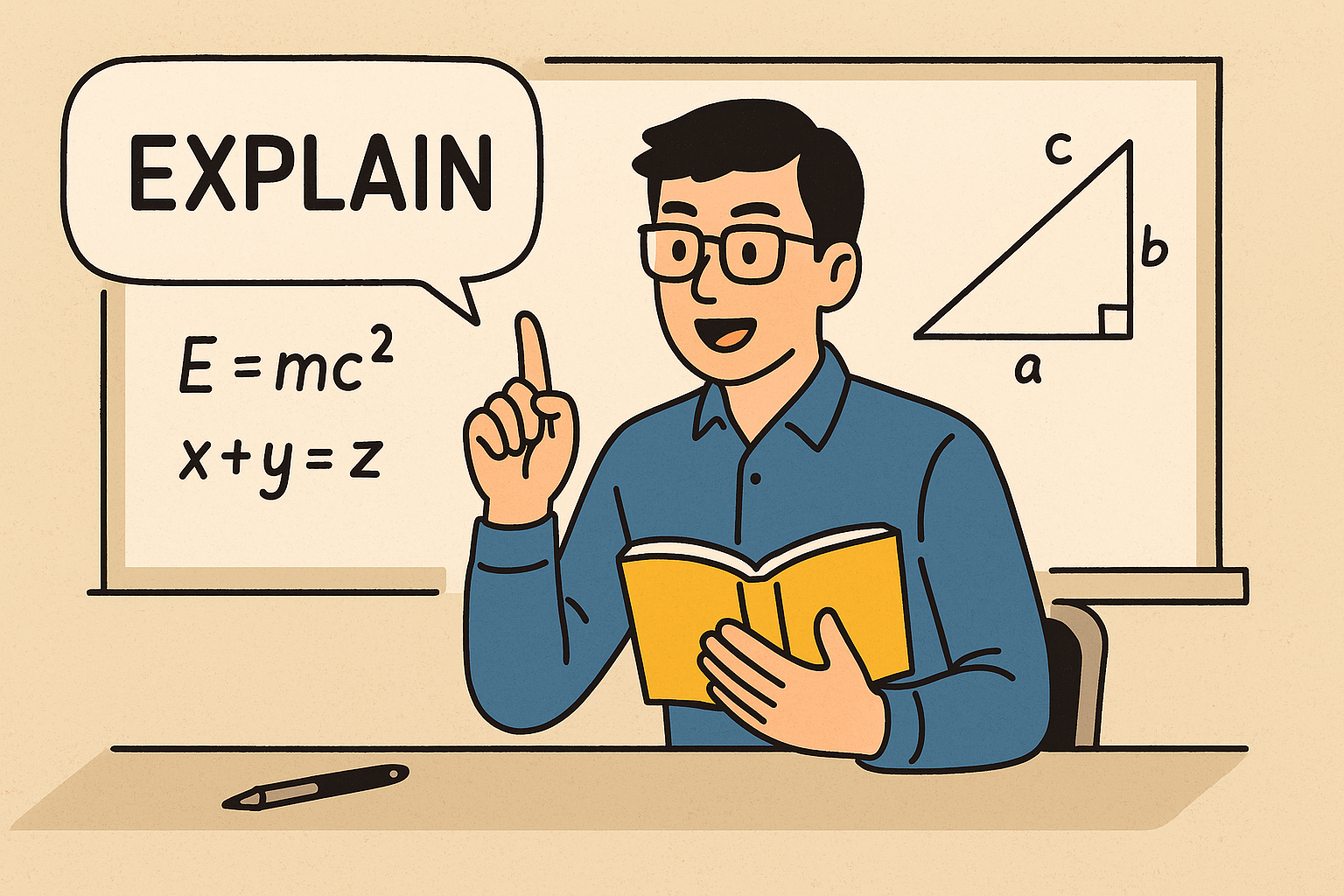「教えられる」より「説明できる」が最強!——中学生・家庭教師・資格マニアの三重視点で考える“理解のゴール”
①導入:親御さんが抱える“よくある悩み”
「うちの子、家で問題集は解けているのに、テストになると点数が取れないんです」
「単語は覚えているはずなのに、英作文になると全然出てこなくて…」
家庭教師をしていると、保護者の方からこうした声をよく耳にします。
これは決して珍しいことではありません。実際、私自身も中学生時代には「わかっているつもりなのに、点数につながらない」経験を何度もしました。
では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか?
そのカギになるのが “説明できるかどうか” です。
「解ける」ことと「説明できる」ことは似ているようで、実は全く違います。
そして“説明できる”力こそが、学力の真のゴールであり、点数アップや将来の学びにつながる一番の武器になるのです。
②先生目線:家庭教師としての実感
私は普段、中学生をメインに家庭教師をしています。
授業をしていていつも感じるのは、「答えは出せるけど理由を説明できない子が多い」 ということです。
例えば、英語の「三単現のs」。
“he plays tennis” は正しく書けるけれど、
「どうしてsがつくの?」と聞くと、言葉に詰まってしまう。
逆に、まだ完璧に暗記できていなくても、
「主語がheだから一人の人を表していて、今のことだから動詞にsがつく」
と自分の言葉で説明できる子は、その後の理解が一気に伸びていきます。
つまり「説明できる」ことは、理解の定着と応用力アップの分岐点 なのです。
だからこそ私の授業では、答え合わせのときに必ず「説明してもらう」時間を設けています。
正解かどうかだけではなく、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で言えるようになることを大事にしているのです。
③生徒目線:エピソードで見る“説明の力”
ある中学2年生の生徒の話です。
最初の頃、その子は英語の文法問題でそこそこ正解できるのですが、私が「どうしてそうなるの?」と尋ねると答えられませんでした。
「なんとなく」「覚えたから」で終わってしまっていたのです。
しかし授業を重ねる中で、私はあえて何度も同じ質問をしました。
「どうして“he play”じゃなくて“he plays”なの?」
「主語がtheyのときはどう?」
最初は苦戦していましたが、あるとき突然スラスラと説明できるようになったのです。
「heは一人の人だから、動詞にsがつくんだよね」
「でもtheyは複数だからsはいらないんだ」
その瞬間から、その生徒は「ただの暗記」から抜け出して、理解を自分のものにしました。
結果的に、定期テストの英作文問題でもミスが激減し、点数も安定して伸びていきました。
④資格勉強での気づき:大人も同じ“説明できる”の壁
実はこの「説明できるまで理解する」という視点は、大人の学びでもまったく同じです。
私は今、中小企業診断士や簿記といった資格勉強に取り組んでいます。
テキストを読むだけなら誰でもできますし、問題集を解いて答えだけ合わせることも可能です。
しかし、本番の試験では「なぜこの答えになるのか」「どういう仕組みでそうなるのか」を理解していないと応用問題に太刀打ちできません。
だからこそ、私は必ず「自分の言葉で説明できるか」をチェックポイントにしています。
例えば、診断士の勉強で出てくる“競争戦略”という用語。
「差別化戦略」「コストリーダーシップ戦略」といった言葉をただ暗記するだけでは頭に残りません。
でも「これは実際の企業でいうと、ユニクロが低価格路線を取るのはコストリーダーシップ。スタバが空間やブランドで付加価値をつけるのは差別化」と自分なりに説明できると、一気に理解が深まります。
つまり、中学生も大人も同じ。
「説明できる=本当に理解している」 ということなのです。
⑤まとめ:親御さんへのメッセージ
ここまで先生として・生徒として・資格受験生としての三つの視点から見てきましたが、結論はシンプルです。
◉ 問題が解けることよりも、説明できることが理解のゴール。
◉ 説明できる力は、暗記に頼らない本物の学力につながる。
◉ その力はテストだけでなく、将来の勉強や仕事にも生きる。
私の授業では、ただ「正解を教える」「暗記させる」のではなく、
「自分の言葉で説明できるようにする」ことを重視しています。
このスタンスがあるからこそ、生徒が自分で考え、自分で答えられるようになり、テストでも力を発揮できるのです。
そして、この学び方こそが、親御さんにとっても「安心して任せられる指導」につながると考えています。
⑥最後に(行動につなげる一言)
お子さんが「なんとなく覚えた」状態から「説明できる」状態へ進むと、学びはガラッと変わります。
もし「覚えているのに点数が取れない」「応用問題になると止まってしまう」と感じたら、それは“説明できる練習”が足りないサインかもしれません。
私は授業を通して、この“説明できる力”を一緒に育てていきます。安心してお任せください。