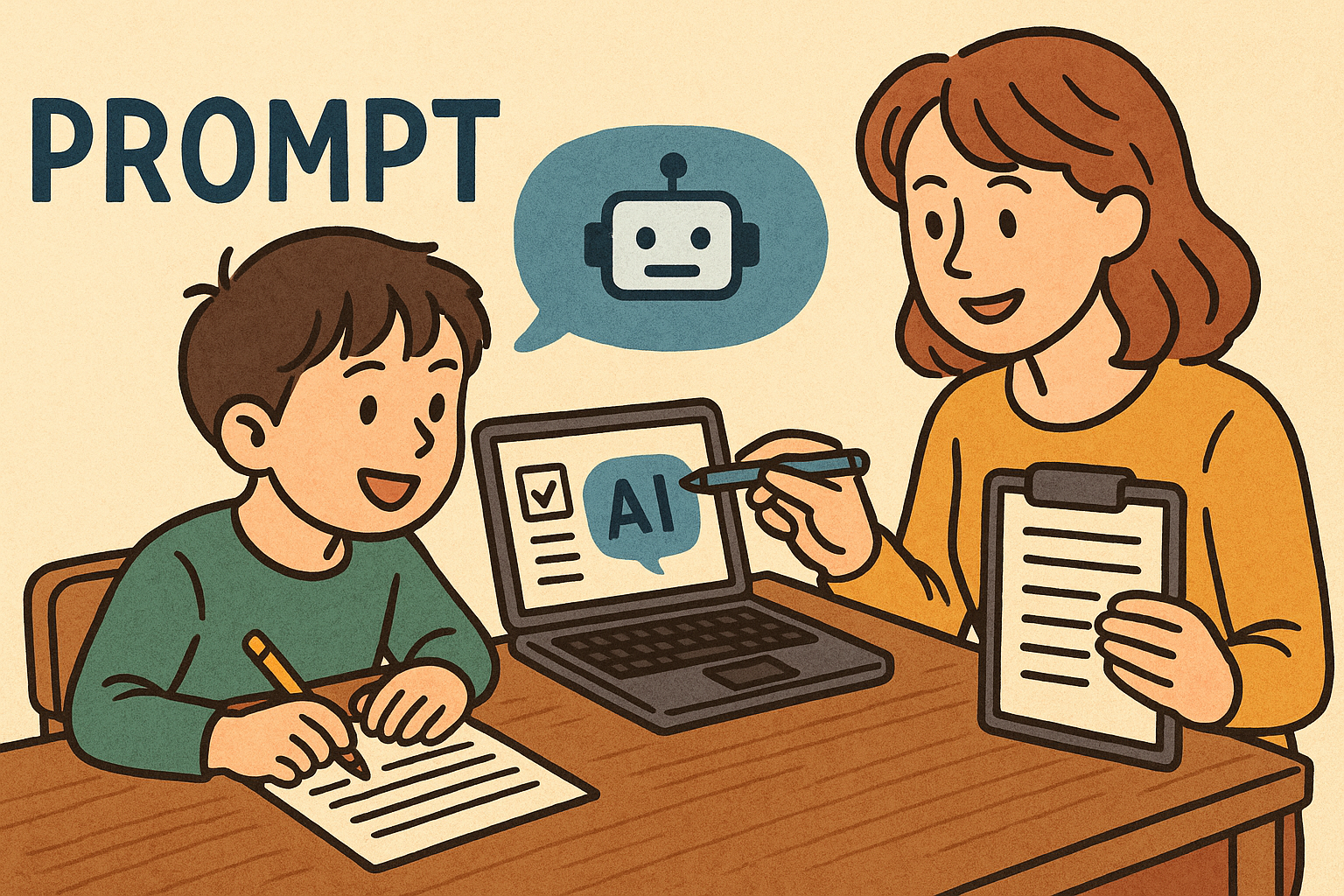ご家庭でのAI活用:プリント作りは「説明力トレーニング」
① なぜプロンプトが大事か
AIにプリントを作らせると便利ですが、実は**「どう指示するか(プロンプト)」** が結果を大きく左右します。
曖昧な指示では
◉ 省略されたり
◉ 難しすぎる問題が出たり
◉ 形式がバラバラになったり
します。
でも逆に、伝え方を工夫すれば驚くほど安定して成果が出ます。
この「伝え直し」の経験こそが、子どもにとって説明力の練習になります。
② プロンプトを整理するコツ(P/N方式)
AIにお願いするときは「ポジティブ」と「ネガティブ」をセットで書くと安定します。
◉ ポジティブ(やってほしいこと)
「中1英語、be動詞と一般動詞の基礎問題を10問、穴埋め形式で」
◉ ネガティブ(やってほしくないこと)
「長文・和文英訳・高校範囲は出さないで」
このように書くと、子どもの欲しい範囲だけがピンポイントで出てきます。
③ 一度に全部お願いしない
AIは「問題+解答+解説+図表」などを一度に頼むと混乱しがちです。
◉ まずは「問題だけ」
◉ 次に「解答」
◉ その後で「解説」
というふうに分割依頼したほうがきれいに整理されます。
よくあるズレと修正プロンプト例(家庭用)
1) 途中で省略される/数が足りない
◉ 症状:10問頼んだのに5問で終わる
◉ 修正プロンプト:
「必ず10問すべて出してください。途中で省略せず、最後に『合計10問』と明記してください。」
2) 形式が違う
◉ 症状:穴埋めを頼んだのに並べ替えが混じる
◉ 修正プロンプト:
「形式は穴埋めのみでお願いします。並べ替え・記述・長文は不要です。」
3) 難易度がズレる
◉ 症状:基礎を頼んだのに発展的な問題が混ざる
◉ 修正プロンプト:
「対象は中学1年生の基礎レベルに限定してください。高校範囲や発展的内容は含めないでください。」
4) 学年・範囲がズレる
◉ 症状:まだ習っていない文法が出る
◉ 修正プロンプト:
「対象は中1。範囲はbe動詞・一般動詞・三単現に限定してください。進行形や不定詞は出さないでください。」
5) 言語が混ざる
◉ 症状:解説が全部英語で読みづらい
◉ 修正プロンプト:
「設問は英語、解説はやさしい日本語で1文(40字以内)にしてください。」
6) 問題と解答が混在する
◉ 症状:問題の下にすぐ答えが出てしまう
◉ 修正プロンプト:
「まず問題だけを出してください。こちらが『解答をください』と伝えるまで答えは書かないでください。」
7) 勝手に要約・省略される
◉ 症状:「20問」と言ったのに「代表10問です」と圧縮される
◉ 修正プロンプト:
「要約や圧縮は不要です。指示通り20問をそのまま提示してください。」
8) 配列が乱れる/番号抜けがある
◉ 症状:番号が飛んだりバラバラに出る
◉ 修正プロンプト:
「番号は1〜20の連番で表示してください。欠番や重複はしないでください。」
9) 重複が多い
◉ 症状:同じ単語やパターンばかり出る
◉ 修正プロンプト:
「重複禁止。できるだけ文型や語彙をバラしてください。最後に『重複語一覧』を出力してください。」
10) 解説が薄い
◉ 症状:「sがつくから正解」程度で理由が足りない
◉ 修正プロンプト:
「各解説には必ず『主語』『動詞』『三単現』などの用語を1つ以上含めてください。40字以内で。」
ご家庭で迷ったときのチェックリスト
① AIの得意なこと
◉ 短文問題の量産(穴埋め・一問一答形式)
◉ レベル帯の切り替え(基礎・標準・応用の使い分け)
◉ 出力を順番に分ける(問題 → 解答 → 解説)
◉ 用語の言い換えややさしい日本語での説明
② AIの苦手なこと
◉ 一度に全部(問題+解答+解説+図表+レイアウト)をやらせる
◉ 学年範囲や禁止事項を守る(指定しないと混ざりやすい)
◉ 厳密な数値計算や図形の作図(必ず手直し前提)
◉ 重複の完全防止(チェックを促さないと繰り返す)
③ ポジティブ/ネガティブ指示の雛形
◉ ポジティブ(必ずやってほしいこと)
「中1英語、be動詞と一般動詞の基礎問題を10問。穴埋め形式で。問題は英語、解説は日本語。」
◉ ネガティブ(やってほしくないこと)
「長文や和文英訳は不要。高校範囲の文法は出さないで。途中で省略や要約をしないで。」
④ ご家庭で守るルール
◉ 一元化しない: 問題だけ → 解答 → 解説の順で依頼
◉ P/Nセット: 毎回ポジティブとネガティブをセットで書く
◉ 検品フック: 出力の最後に「合計〇問」「対象学年」を自己申告させる
まとめ:AIとのやり取りは説明力を伸ばす最高の教材
AIを家庭学習に取り入れるとき、
◉ 指示がずれる
◉ 省略される
◉ 難易度が合わない
といった「ちょっとした失敗」は必ず起きます。
でも大切なのは、そこで「もう使えない」と切り捨てるのではなく、
「どう伝え直せば思い通りになるか?」を親子で考えること。
この試行錯誤そのものが、子どもの “説明できる力” を育てる練習になります。
AIはただの便利ツールではなく、親子でコミュニケーションしながら「指示力・説明力」を伸ばす最高の教材にもなるのです。
親御さんへのメッセージ
◉ 子どもが「ただ覚える」から「説明できる」へ進むと、学びは一気に深まります。
◉ プリント作りやAI活用は、その練習を家庭で楽しく実現できる方法です。
◉ 私自身の指導でも「解けるより説明できる」をゴールにしています。
だから、安心してお任せください。
お子さんが「説明できる」ようになる瞬間を一緒に作っていきましょう。