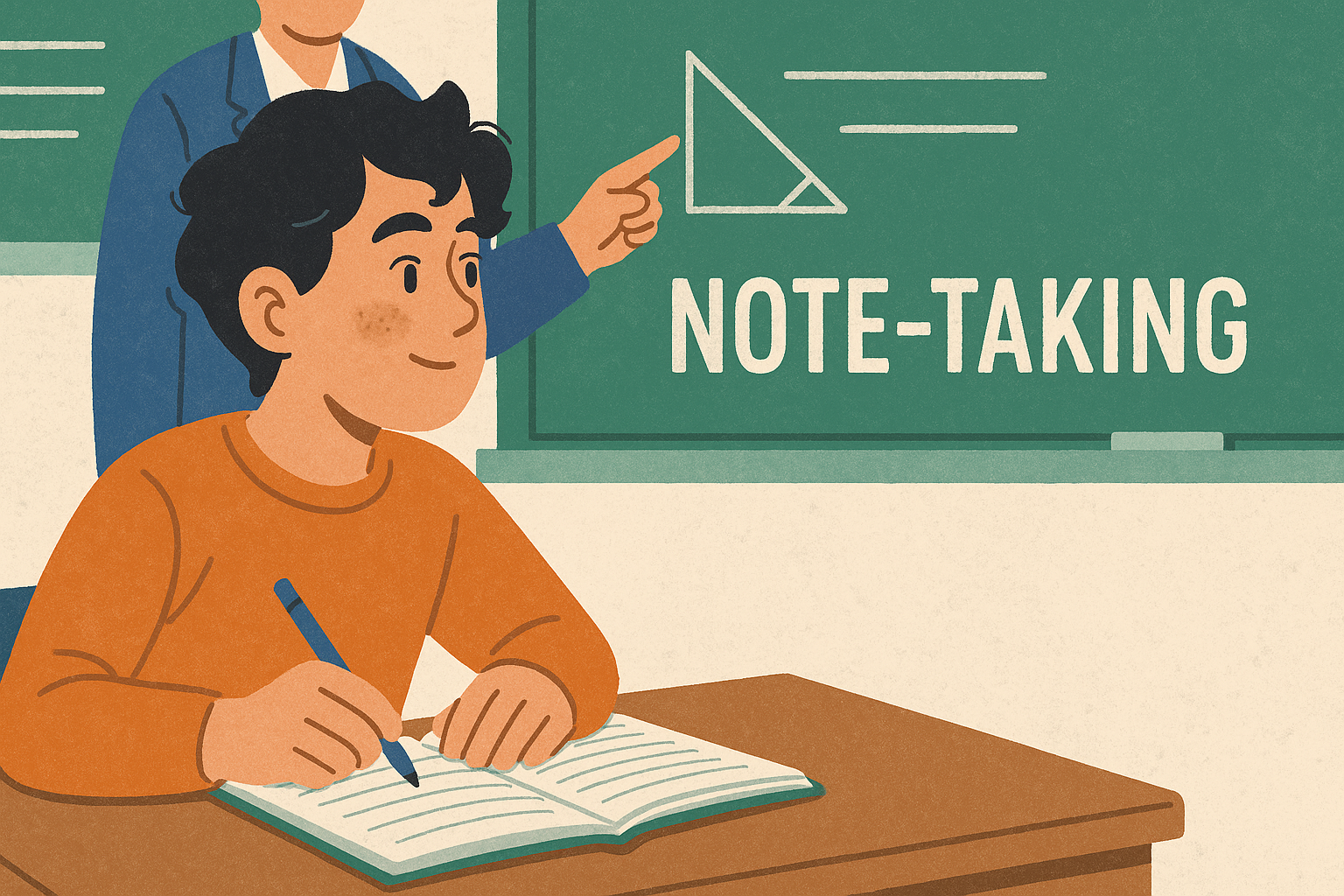学校の授業を最大化する勉強法シリーズ第1回:ノートの取り方
📚 はじめに
塾や家庭教師のブログでは「家庭学習のやり方」や「受験テクニック」はよく見かけます。けれど、実際に生徒が一日の中で一番長く過ごしているのは 学校の授業 です。
この“必ず毎日ある時間”をどう活かすかで、学力の伸びは大きく変わってきます。
そこでこのシリーズでは、僕が家庭教師として多くの生徒を見てきた経験、そして自分自身が学生時代に試行錯誤した体験をもとに、「学校の授業を最大化する勉強法」 を紹介していきます。
第1回のテーマは 「ノートの取り方」。
単純に「きれいに書く」ことがゴールではありません。ノートは“後から見返すと授業を再現できるツール”であってほしいのです。
❌ よくある失敗パターン
まず、よくある失敗例から。授業中の生徒のノートを見ていると、こんな傾向が目につきます。
◉ 板書された内容を、ひたすら写経のように書き写す
◉ 文字はきれいで丁寧だが、実際には頭に残っていない
◉ 自分の言葉がなく、ただのコピーになっている
これは一見すると「真面目でよくできている」ように見えます。保護者から見ても「ノートがしっかりしていて安心」と感じるかもしれません。
しかし、実際にはこのタイプのノートは 復習に使えない ことが多いのです。なぜなら「どこが大事なのか」「どういう流れで話が進んだのか」が見えなくなってしまうからです。
✍️ 僕自身の失敗と気づき
正直に言うと、僕自身も学生時代に同じことをしていました。黒板の文字を全部ノートに移す。それだけで「勉強した気分」になっていたんです。
でも、いざテスト前に見返すと…
「大事なところがどこなのか、さっぱり思い出せない」
「ノートはあるのに、授業の中身が頭から抜けている」
そんな経験を何度もしました。
そこから少しずつ工夫を加えていきました。僕が実践して効果があった方法はこうです。
◉ 先生が「ここ大事だよ」と言った部分は、必ずノートに書き、枠や印をつけて目立たせる
◉ 単元のまとめを書いているときはしっかり耳を傾け、できるだけそのまま記録する
◉ それ以外の部分は、全部書き写すのではなく、自分の言葉で箇条書きに整理
◉ あとで見返したときに授業の流れが追えるように、自分なりのつながりを意識して書く
◉ コーネル式ノートのように、書く場所をあらかじめ分けておき「まとめ欄」「メモ欄」を作る
こうして取ったノートは、単なる「文字の記録」ではなく、授業をもう一度なぞれる地図になっていきました。
⚖️ 板書と先生の話、どっちを重視?
僕の答えははっきりしています。
「全部は写さない」。
なぜなら、黒板に書かれているポイントはほとんどが教科書に載っているからです。
もちろん板書を無視していいという意味ではありません。むしろ「核」となる部分はきちんと押さえる必要があります。ただ、そこだけに意識を向けてしまうと授業の“生の価値”を取り逃がしてしまうのです。
授業の一番の特徴は「先生の解釈」「その場の説明」「具体的な例え話」です。
つまり大事なのは次のような部分。
◉ ポイントにたどり着くまでの過程
◉ 他の視点ではどう解釈できるかという補足
◉ 自分が「これなら理解できる」と感じた表現
これらをノートに落とし込めるかどうかが、学習の深まりを左右します。
📈 生徒が伸びたエピソード
ある中学生にこの方法を伝えました。最初は「全部書かないと不安」と言っていた子でしたが、勇気を出して切り替えた結果…
◉ 家でノートを整理する時間が大幅に減り、その分を問題演習に回せるようになった
◉ 「先生が言ったことをメモする」習慣がつき、授業を聞く集中力が上がった
◉ 苦手だった社会の点数が 30点以上アップ
ノートは「授業中の写し取り」ではなく「授業内容を理解する道具」に変わり、そのまま成績向上につながった実例です。
😥 損をしている真面目な生徒たち
一方で、真面目で几帳面な生徒ほど「全部書かないと心配」になってしまいます。
結果として、ページは文字で埋まっているのに「どこが大事なのか」がわからないノートになっているのです。
実際に授業で重要なのはこの3つ。
◉ 授業の最初「今日はこれをやるよ」という切り出し
◉ ポイントと、そのポイントに至るまでのルート
◉ 授業の最後のまとめ(=テストに出やすい部分)
極端に言えば、この3つが押さえられていれば十分。
細部を完璧に残すことよりも「要点をつかむ力」を養う方が、長期的には圧倒的に役立ちます。
👨👩👧 親御さんへのチェック法
「ノートの内容なんて自分にはわからない」という保護者の声もよく聞きます。
でも実は、専門知識がなくても簡単にチェックする方法があります。
◉ ノートを見せてもらい、「このノートを使って授業をしてみて」とお願いする
◉ 子どもがスムーズに説明できれば、そのノートは正しく機能している証拠
◉ 説明できないなら、ノートが“写すだけ”になっている可能性大
親御さんが授業内容を理解している必要はありません。むしろ「知らないからこそ」説明させやすいんです。説明できるかどうかで、理解度とノートの質が一目でわかります。
📝 理想のノートとは
僕が考える理想のノートはとてもシンプルです。
「自分が見返したときに、その授業をノートだけで再現できること」
それさえできていれば、細かい見た目や装飾は関係ありません。ノートはアート作品ではなく、自分の学びを積み上げるツールだからです。
✅ まとめ
◉ ノートは写経ではなく、自分の言葉で流れを整理する
◉ 板書よりも「先生の言葉」や「解釈」に注目する
◉ 復習時間を減らしてテストに直結する情報を残す
◉ 親は「ノートで授業を再現できるか」でチェックする
次回は 「授業の聞き方」 を取り上げます。
学校生活をちょっと工夫するだけで、勉強はもっとラクに、もっと効果的になります。