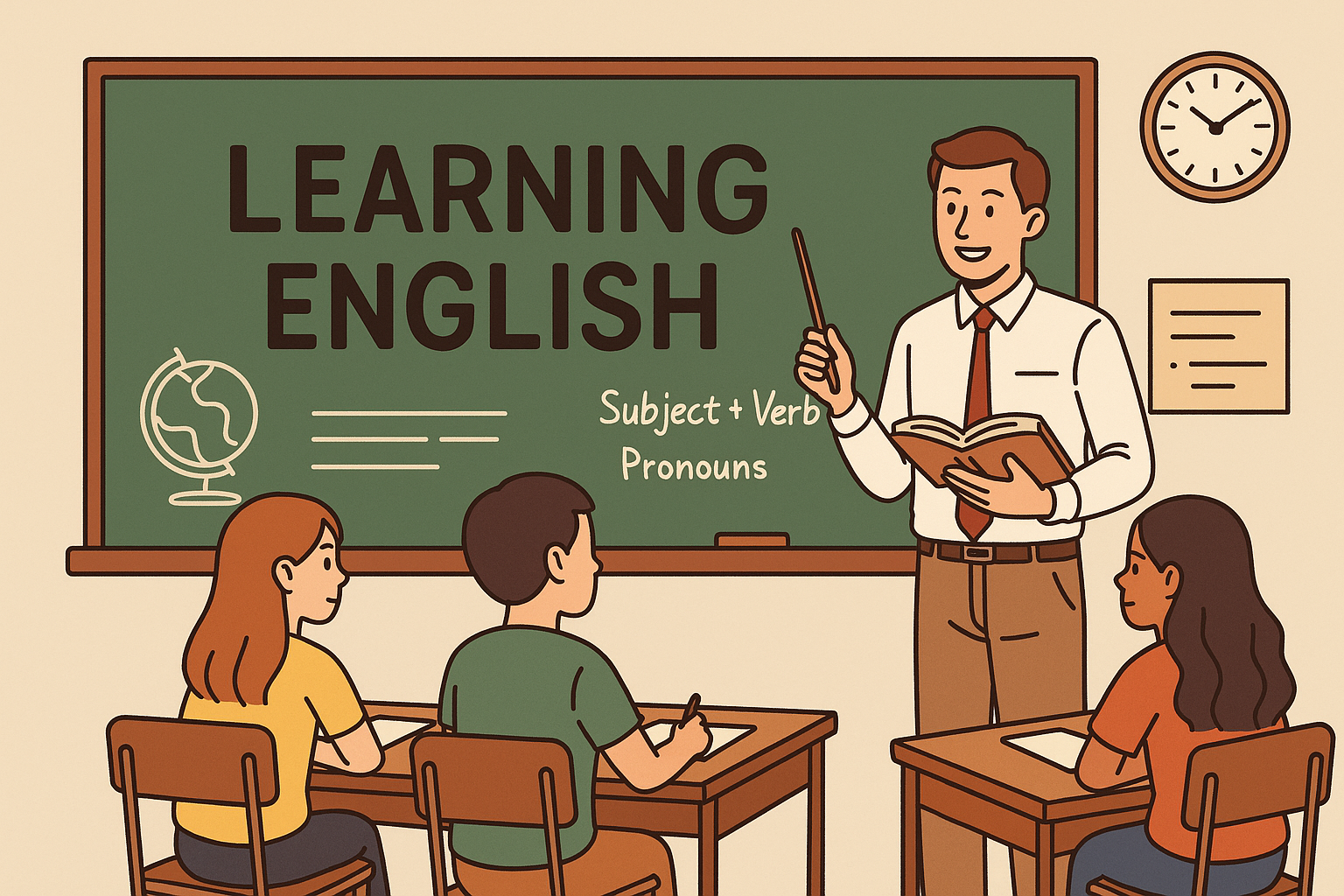学校の英語授業編第1回:「なんとなく英語」の授業の現実
📚 はじめに
「英語の授業って、今は随分変わったんだなぁ」
今の、生徒さんを見ていて僕自身が感じる気持ちです。
僕自身が中学生だった頃、授業は基本的に「文法の説明」や「訳読」が中心。ところが今の中学校では、グループワークやスピーチ、CD音源を使ったリスニングなど、当時にはなかった活動型の授業が取り入れられています。
表面だけ見れば「生きた英語に触れられるようになった」と思えるのですが、現場を見ているとどうしても気になる点が出てきます。
それが 「なんとなく英語」 に陥ってしまう危うさです。
生徒は一見、活動を楽しみながら授業を受けているように見えます。しかし、文法や品詞といった基礎的な土台が十分に説明されないまま進むため、結果的に「なんとなくわかった気がする」状態で終わってしまうことが少なくありません。
ここで強調しておきたいのは、これは学校や先生を批判する意図ではないということです。
僕はあくまで家庭教師として、生徒さんのノートや宿題、テスト結果に向き合う立場から「実際にこういう課題がある」と感じているだけです。現場の先生方も制度やカリキュラムの中で最大限努力されていることは理解しています。この記事では、その上で「生徒目線でどう見えているか」「家庭教師の立場から見えてきた事実」を共有したいと思います。
❌ 実際の授業例:スピーチ課題の裏にある落とし穴
印象的だったのは、ある学校で出された宿題です。
テーマは 「自分の好きなことを英作文にしてスピーチする」。
一見、とても魅力的な課題です。生徒の個性が表れ、自分の考えを英語で伝える練習になる。英語を“使う”力を育てようとする意図が伝わってきます。
ところが、実際に生徒が取り組もうとすると問題が浮き彫りになります。
スピーチで最低限必要なのは、
◉ 文法(時制、接続詞、語順のルール)
◉ 文型の基本理解(SVOなどの土台)
◉ 表現の幅を広げるための例文や型
こうした要素です。ところが授業や教科書では、雛形の例文こそ載っているものの、細かい文法解説や体系的な指導はほとんどありません。
その結果、生徒は「なんとなく見様見真似」で文章をつなぎ合わせてスピーチを仕上げるしかなくなります。
せっかく良い課題なのに、指導の部分が不足しているために、完成度は低く「なんとなくで終わる」。とてももったいない実態です。
😕 生徒の学び方が「なんとなく」で止まる理由
最近の授業ではグループワークやCD音源を使ったリスニングなどが多く取り入れられています。活動型で一見良さそうに見えますが、実は 文法や品詞といった基礎を体系的に扱う時間がほとんどない のが現実です。
つまり、生徒たちは「英文をどう構造的に理解すればいいのか」を十分に学ばないまま、活動に取り組んでいることになります。
その結果…
◉ 教科書に出てきた例文なら「なんとなく」意味がわかる
◉ 書かれている英文をマネして「なんとなく」作文できる
◉ でも少し違う形や捻った問題が出ると手が止まる
こうして「なんとなくでできる範囲」から抜け出せずに、成績の伸び悩みに直結してしまいます。
🚧 「なんとなく英語」が生む弊害
さらに怖いのは、この「なんとなく英語」が続くと生徒の気持ちに悪影響を与えることです。
◉ 「自分は何のためにやっているのかわからない」
◉ 「形だけの作業をさせられている気がする」
◉ 「結局わからないまま進んで、英語が嫌いになる」
英語が好きな生徒であれば、自分で参考書や問題集を補って前に進めるかもしれません。けれど、英語にそこまで強い興味がない生徒にとってはまさに地獄です。努力しているつもりでも結果がついてこないので、どんどん自信を失ってしまいます。
🧑🏫 家庭教師の現場から見えた実例
僕が家庭教師として教えてきた中で特に印象的なのは、学校の定期テストではある程度点数が取れているのに、模試や入試の過去問になると全く歯が立たないケースです。
なぜかというと、定期テストは「出るところが決まっている」ため、なんとなくの理解でも答えられてしまうからです。しかし範囲が広がる模試や入試では、応用的な問題が出てきます。すると、基礎が曖昧な生徒は「当てずっぽうで答える」しかなくなってしまうのです。
これは決して珍しい話ではなく、多くの公立中学生に共通する傾向だと感じています。僕自身の経験では、指導した生徒のうちかなりの割合で「文法や品詞を最初からやり直す必要」がありました。
📝 一言まとめ
繰り返しますが、これは学校の先生方を批判するために書いているのではありません。制度や時間の制約の中で、先生方は工夫を凝らして授業をされています。
ただ現実として、家庭教師として生徒と向き合うと「なんとなく英語」にとどまってしまっている姿を多く目にします。そしてその状態では、やはり「なんとなくの結果」しか出せないのです。
なんとなくで終わらせず、どう自分の理解に結びつけるか。
ここを意識することが、英語を本当に自分の力に変えるための第一歩になります。