「AIでプリント作りに挑戦する前に知っておきたいこと」
2025/8/22
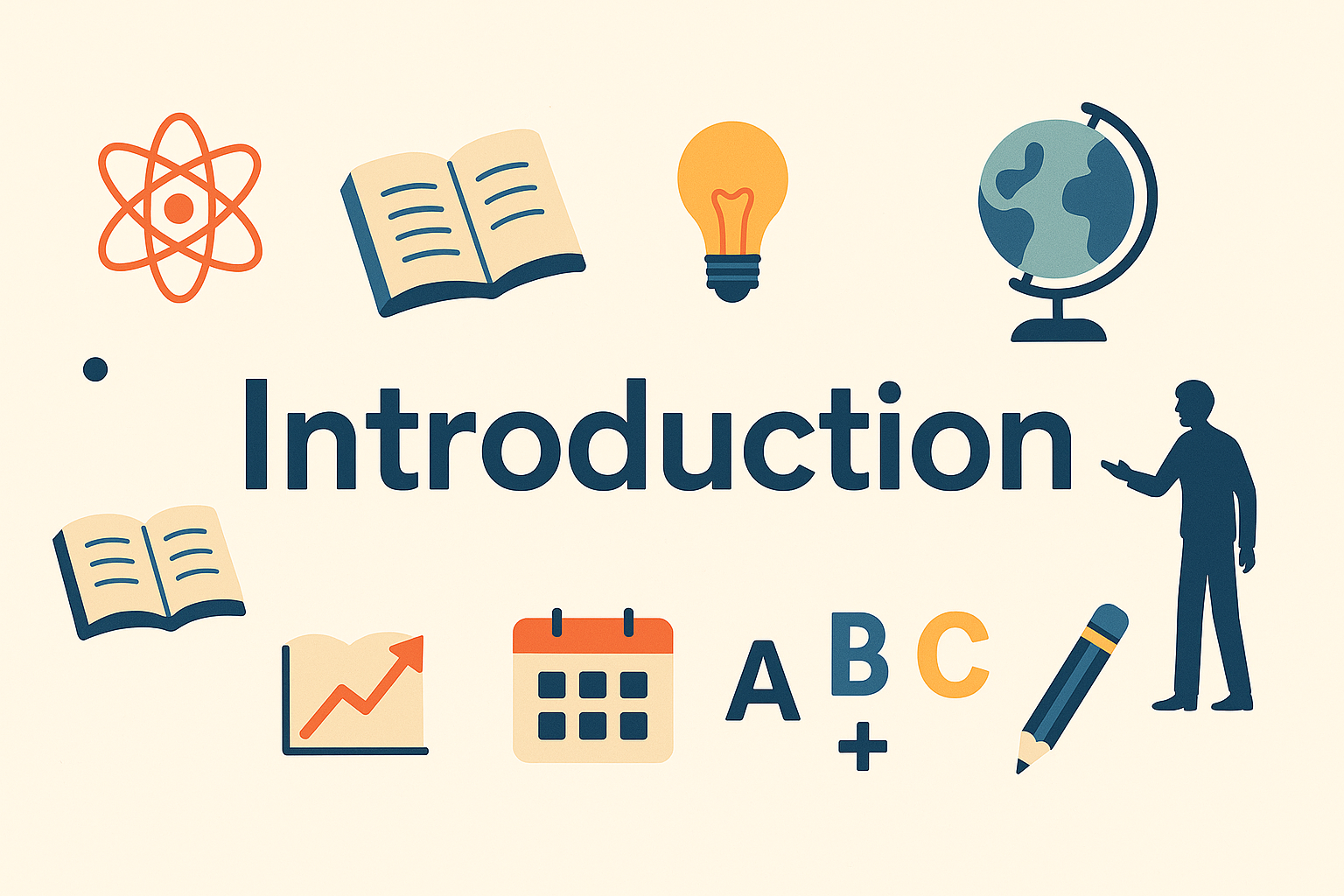
近年、AIを活用して学習プリントを作ろうとするご家庭が増えています。
実際に指示を与えるだけで教材の形はすぐに出力できるため、「自宅でも教材を用意できるのでは」と考える方も少なくありません。
しかし、実際に取り組んでみると次のような課題が見えてきます。
◉ 学習順序の整理が難しい:どの単元から、どの流れで扱うかが曖昧になりやすい。
◉ 問題構成の一貫性不足:穴埋め・選択・記述などのバランスや難易度が揃わない。
◉ AI特有の不正確さ:事実と異なる内容や、指示から逸れた出力が混ざる。
こうした課題を解決するには、単にAIを利用するだけでなく、教育的な視点での検証と調整が不可欠です。
つまり「整えて学習に活かす」段階こそが、人間の教師に求められる役割になります。
そこで本シリーズでは、私自身がAIと試行錯誤しながらプリントを構築したプロセスをもとに、家庭で実践する際に押さえるべきポイントを整理していきます。
◉ 第1回:ロードマップの作り方
◉ 第2回:問題構成の考え方
◉ 第3回:指示内容の工夫
◉ 第4回:見切り発車させるタイミング
「AIでプリントを作れること」と「子どもの学習効果に結びつけること」の違いを、ぜひ一緒に確認していきましょう。
次回は第1回、**「ロードマップの作り方」**を解説します。
ここから具体的なステップに入ります。
この先生の他のブログ
「AI任せ」ではありません。私が大切にしている“学習設計”という指導
2026/1/15
「AI任せの先生」ではありません最近、「AIを使って指導しています」と言うと、「AIが勝手に教えてくれるの?」「先生は何をしてくれるの?」と感じる方もいると思います。先に結論を書きます。授業の判断と責任は、すべて私が持ちます。AIは、学習記録の整理や振り返りの補助など、裏方として使うことがあるだけで...
続きを読む
AIを使って家庭で回る英語教材を作る4回完結コースのご紹介
2026/1/8
こんにちは!!マナリンクで中学生をメインに指導をしているタケウチです!!忙しくて(言い訳ですが笑)だいぶブログの更新をしておりませんでした。2026年最初のブログは新規作成したコースの紹介になります。家庭で回る英語教材を4回で完成させるコースを作りました。テーマは一言でいうと「英語を教える」のではな...
続きを読む
🌟 宿題をAIで“焼き増し”するという発想 〜家庭でできる「うちの子専用プリント」のつくり方〜
2025/11/7
👀 「この問題、もう1回やらせたい」って思ったことありませんか?家庭でお子さんの宿題を見ていて、「もう一度やらせたいな」と思う瞬間、ありますよね。でも実際にやろうとすると──◎ 同じ問題を書き写すのは面倒◎ 数字を変えたいけど文章題は作り替えが難しい◎ 市販ドリルの問題は似てるけど“微妙に違う”この...
続きを読む
💡AIと一緒に「学び方」を設計する時代へ 〜生徒一人ひとりの特性に合わせた授業づくり〜
2025/11/2
こんにちは、家庭教師のタケウチです😀私は本業で【診療放射線技師】として医療現場に勤務しながら、中学生中心に10年以上、家庭教師を続けています。ここ最近は、「AIをどう教育に活かせるか?」というテーマに挑戦しています。単に教材を作るだけではなく、**“学び方そのものを設計する”**というアプローチです...
続きを読む