#25 古文単語の暗記術・参
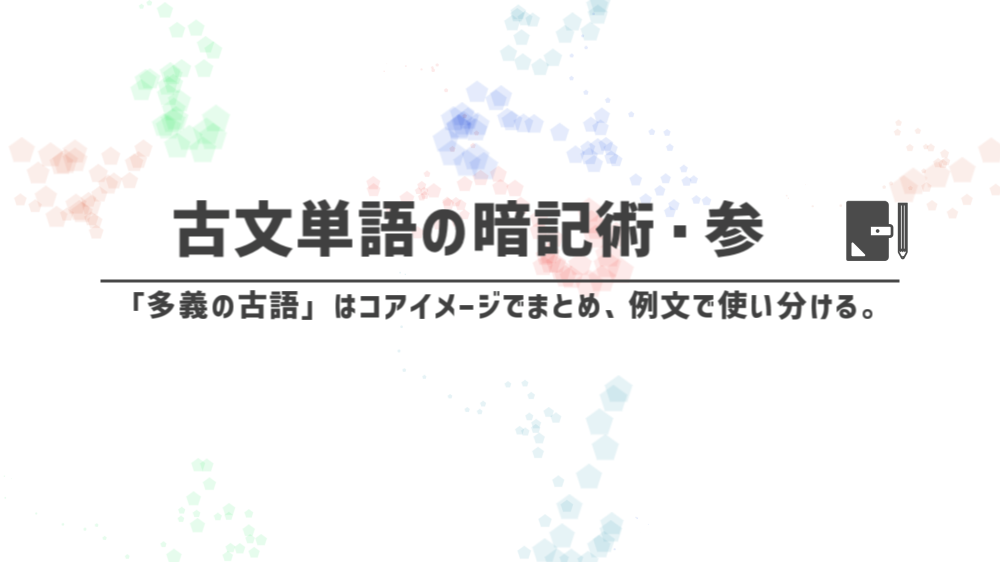
この記事は、300語程度の古文単語帳を活かす方法の続きです。
「古文単語の暗記術・弐」も併せてご覧くださいね。
古文が苦手な人向けに単語の覚え方を紹介しています。「シンプルに反復」「単語と意味に接着剤」に続いて、今回は多くの受験生がつまづくポイント「多義の古語」をどう覚えていくかのか、まとめます。いくつも意味があって、文脈に応じて適正な意味を選ばなければなりません。
💬多義の古語とコアイメージ
ここでは、一単語に三つ以上の意味がある場合を多義と定義しておきます。
▶おとなし:「大人らしい」だけじゃない!
おとなし[シク活用]
①大人らしい。大人びている。
②年配だ。(年長で)主だっている。
③(年配で)思慮分別がある。
いいずな書店『わかる・読める・解けるKey&Point古文単語330』
この単語は現代語にも良くにているので「大人だってことだな」と一つ目の意味は分かりやすいですね。でも二つ目の「主だっている」や三つ目の「思慮分別がある」が入ってくると「情報量過多だ👀💦」となりがち。前の記事で紹介した「3点整理法」で繰り返し繰り返しやっても、なかなか頭に入らないという人多いと思います。覚えても、時間経過とともに忘れやすいのも痛いところ。
⚠️多義語暗記の落とし穴
一単語に一つ、二つの訳し方を覚えても、入試では通用しないことがあります。
なんでかというと、選択肢には代表的や訳し方を言いかえた表現が使われたり、多義語のもついくつかの意味から、マイナーな方が使われたりするからです。ただでさえ覚えておくだけで大変な多義語ですから、対応策を考えないと。
👦「現代語訳に、言い換え表現を調べて書き足す…?」
👧「稀にしか出ない意味に時間をかけることになりそう…。」
💡コアイメージをつかむメリット
コアイメージといういのは、その単語がもつ中心的な意味やニュアンスのことです。上記の「おとなし」では【幼稚でない大人らしさ】と紹介されています。ただ、これだとまだイメージではないので、自分の身近な例で具体的にイメージしてみましょう。
💭「おとなし」を身近なリーダーと関連付け
この単語は「大人らしい」大人にも使えれば、「大人びた」青年にも使えます。年齢がそこまで高い必要はないようです。ある集団の中で、リーダーを引き受ける人を想像します。学級委員長でも部長でも顧問でも学年主任でも部長でも社長でも良いんですが、自分の身近な人でイメージ。
- 年齢は相対的に上
- 一定の気配りができるから長になった
- 立場上、経験値が周囲より高い
「大人らしい」「主だっている」「思慮分別がある」を包み込む感じでイメージと関連付けてみましょう。単語と人物像が結びついていれば、沢山ある意味も想起しやすいはずです。
💭単語帳にある訳し方そのものが選択肢にない時は
例えば「思慮分別がある」ではなく「物事をわきまえている」だったら。
または「主だっている」ではなく「中心的な立場だ」だったら。
一見、自分の知っている訳し方がない場合でも、コアイメージに一番近く、同時に文脈上自然と言えるものを選ぶことができます。少し難しいかもしれませんが「表現上の一致」ではなく「表現対象の一致」を探せばよいということですね。
💬例文活用のポイント
例文は単語のコアイメージを確かめるため、そして使い分けの練習をするために活用しよう!
⚠️いきなり例文で覚えるのは悪手
「例文で覚える」という標語は、良く聞こえてきます。しかし、多義の古文単語を文脈で使い分けるのに「例文から入る」というのはお勧めできません。それは文脈は1文程度の短さでは正確に把握できないからです。仮に例文とその意味を覚えたとしても、どうしてその訳し方を選んだのかが、いまいちピンとこないで終わる可能性が高いですし、例文に含まれるほかの単語に目移りして、今一番大切な単語がおろそかになりかねません。
👨「例文を意味の使い分けの練習にするには条件がある」
💡例文はアウトプットに
覚えた意味を「答える」ための問題として例文を活用しましょう。テスト形式にした方が覚えやすいですから、例文の赤文字の部分を赤フィルムで隠して言えるようにするというのはシンプルに効果が高いですね。この方法では「こういう場合はこっちの訳を使う!」というような使い分けの練習には、残念ながらなりません。
また、古文単語にも「呼応」があります。「ゆめゆめ+禁止」「いかで+意志・願望・命令」等、他の語とセットで使う場合が多い単語なら、そのつながりごと音読して覚えられる点がメリットですね。文章で音読する題材としても良いです。
⭕意味の使い分けは「中文以上」で
これが条件です。文脈というのは一文では発生しません。
まとまった量の情報と結びついてできあがるんです。
- 出典とジャンル
- 場面設定や人間関係
- そこに至るまでの話の流れ
現代日本語でも英語でも基本的なことは同じです。つまり【TPO】のようなものですよね。Time、Place、Occasion。英語学習で、ある単語の意味をつかもうとする時も同じです。「え?それってどういう時につかう言葉なの…?」とニュアンスを考えたことがあるでしょう?
だから、「代表的な意味」「古今意義語」「多義語」の大まかな意味を覚えたら、次は文章を読むなかで文脈を探り、訳し方を決定する練習をしていくのがベストですね。こうした使い分けの練習には、Z会の「速読古文単語」など長めの例文が紹介されている参考書がおすすめです。
最後に多義語の極端な例を紹介して終わります。
気色ばむ[マ行四段活用]
コアイメージは「ある感情を表に出す」。「ばむ」は「だつ」「めく」のようにある性質を帯びるという意味の接尾語です。ある感情の部分は、状況によっていろいろな意味になります。これはむしろ多義語というより、状況に応じて臨機応変に意味を表す"代動詞"と呼ぶべきですね。
① 得意げな表情になる
② 相手に好意を示す
③ 機嫌が悪くなる
④ 殺気を放つ
⑤ 緊張が走る
💬まとめ
なんだか、小難しい話になってきたな…と思ったそこのあなた。
今回の記事は「単語の覚え方の基礎」からスタートしたんですが、「意味を絞る」ことからはじめて、「古今意義語」と「多義語」を経由、そして最後に「文脈に沿って読む」ところに来たわけですね。こういうことを考えて文章を読んでいるのが中・上級者。ここまで読んでもらった皆さんには、その道筋が見えたと思います。
高校で使っている300語収録ぐらいの一般的な単語帳。
使い方次第で、十分有効活用ができます。そこに書いてある、見出し語、意味、コアイメージ、例文、関連語などの情報から、自分に必要なものを選び、目的に合わせて活用する意識をもって下さい。参考になりましたでしょうか。是非、自学自習に生かして下さい。ではまた。