AIと社会科学習① ― AI×講師でオーダーメイド教材をー
リョウです。
しばらくは生成AIと社会科の学びについて書こうと思います。最近何かといろんなところで聞くの生成AIですが、社会科の学びに活かすことができるとしたらどう使えるのか。私の授業ではどう使っているのか。みたいなコトを少しずつ書いていこうと思います。皆さんの学習のヒントになれば嬉しいです
第1回目の今日は学習を深めるうえで大事な「問題演習」としての利用です
自分専用にカスタマイズされた問題集に
市販の問題集では、お子さんの苦手分野や進度にぴったり合わないことがよくあります。
生成AIを使えば、その日の学習内容や理解度に合わせて「オーダーメイドの問題」を用意できます。
たとえば…
「自由民権運動から憲法制定までの流れを整理する10問セット」
「江戸時代の改革(享保・田沼・寛政・天保)の違いを比べる選択問題」
「近代の国際関係を、出来事の順番で並べる問題」
といった具合に、学校の進度やテスト前の復習に合わせて柔軟に出題できます。
さらに、間違えた答えも記録しておけるため、「試験前に苦手なところを重点的につぶす」ことが簡単にできます。
もちろん生成AIに丸投げしているわけではありません。講師が必ず内容をチェックし、学びの狙いに合わせて修正や調整を行ったうえで使用しています。
対話しながら深める授業
授業では、ただ生成AIの出した問題を解いて丸付けして終わりにはしません。
解いただけでなく、自分の考えを言葉にする練習 を重ねることを大切にしています。
「どうしてそう考えたの?」「この出来事の背景には何があったと思う?」といった問いかけを通じて、社会科を単なる知識の暗記ではなく、自分の言葉で説明できる理解 へとつなげます。
さらに選択肢問題の場合には、正解だけで終わらせず、「他の選択肢は何だった?」「なぜそれは違うの?」 と確認することで、知識のつながりを整理できるようにしています。
授業の一場面から
たとえば「享保の改革」を学んでいるときのやり取りです。
Q(生成AIによる選択問題例)
享保の改革で実施された政策として正しいものはどれか。
A. 上米の制
B. 株仲間の解散
C. 棄捐令
D. 人返しの法
生徒の答え
「Aの上米の制かな。」
講師の問い返し
「正解!……でも、上米の制って具体的にはどんな仕組みだったっけ?」
生徒の答え
「大名が幕府に米を納めて、その代わりに参勤交代を少し楽にしたんだと思います。」
講師のさらに問い返し
「その通り。じゃあ残りの選択肢はどの改革のときに出てきた政策だったかな?」
ここで一緒に確認すると、
・株仲間の解散 → 天保の改革
・棄捐令 → 寛政の改革
・人返しの法 → 天保の改革
と整理でき、各改革の違いも復習できます。
【ちょっと脱線も…?】
この授業の締めくくりには、生成AIで作成した「享保の改革まとめ絵本」を一緒に見て振り返りました。文字と絵を組み合わせることで、知識がストーリーとして印象に残りやすくなり、生徒も「ちょっと面白い」と感じながら学べることもあります
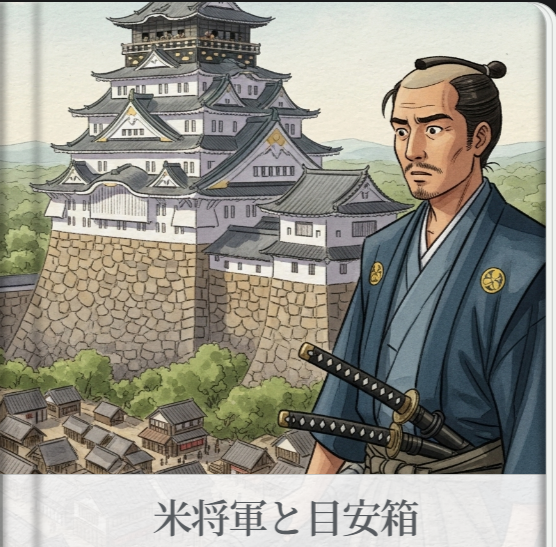
(「享保の改革なのになぜ天守閣があるんだ」とか表紙だけでも突っ込みどころはあるんですけどね…)
まとめ
いかがでしょうか。生成AIは普段の利用だと何か困ったときに「便利に答えを出す道具」と思われがちですが、授業の中では 「考えるための良い問いをつくるパートナー」 になります。
とはいえ、自分一人だと問いが難しくなりすぎることや解説が必要な箇所もあります
生成AIに丸投げするのではなく講師がしっかり調整を加えることで、
・生徒さんには「社会科を自分の知識として理解できる体験」・「間違った知識の獲得防止」
・ご家庭には「安心して任せられる学びの環境」
をお届けしています。
社会科の学習でお役に立てることがあればご相談・体験授業も含めお待ちしております。
Xアカウントを開設しました。
リョウ先生@AI活用×社会科講師( @ryo_asomanabi )

