【韻律の中へ】時計の針はするどく光る
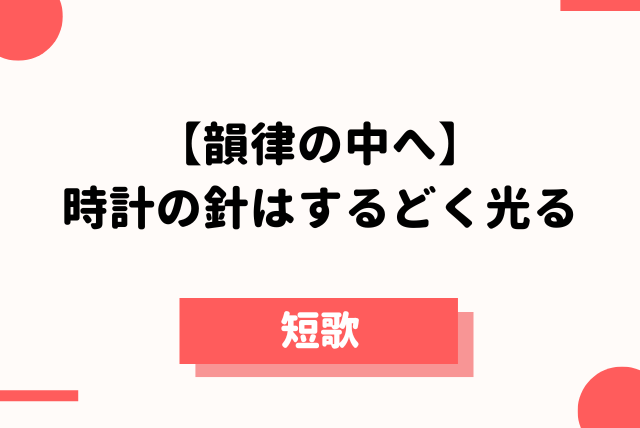
みなさんは、表現についてどの程度自覚的に文章を読んでいるでしょうか。
たとえば、北原白秋さんの短歌にこんな短歌があります。
「時計の針Ⅰ(いち)とⅠ(いち)とに来(きた)るときするどく君を思いつめにき」
この短歌は、時計の一時五分に長針と短針が来た時に、君のことを思い出す、という内容の短歌ですが、
問 どうして「するどく」思っているのか、「するどさ」はどのように表現されているか
と聞かれたとき、自分なりにこたえられるでしょうか?(・・?
この短歌を恋愛の短歌だととらえてもいいし、どのような関係の二人なのかは自由な解釈が可能です。
一方で、作者は、その「思い方」に限定をつけています。それは「するどく」思っているということです。
だから、何かしらの切実さを伴った関係性であることを読み取る必要があります。
そうすると、なぜ12:00ではなく1:05なのかもなんとなく合点がいくかもしれません。
きれいに長針と短針が重なる時刻ではなく、すこし長針と短針がずれてしまうこの時刻。
これが二人の関係性です。もうすこしで重なるのに、重ならない、その時刻を作者は、鋭く見つめています。まるで重なることが許されないかのように、、、。
短針を長針が追いかけます。作者はどちらに自分を重ねているのでしょうか。
みなさんはどう思いますか?
また、もう一つ、考えなくてはいけないのは、「するどさ」を言葉でどう表現しているか?ということです。
韻律は声に出して読むことが必須です。そうすると、
「時計の針Ⅰ(いち)とⅠ(いち)とに来(きた)るときするどく君を思いつめにき」
カ行の音が多用されていることに気づくでしょうか?
特に最後の、「にき」(完了の助動詞「ぬ」の連用形+過去の助動詞「き」の終止形)に古語が使われている理由もカ行を使いたかったからかもしれないと想像がつきますね。
きっ、きっ、と音の中でもするどさを表現しています。
この音の工夫は和歌の時代からずっと受け継がれている日本語の秘密ですし、どの韻律にも音を工夫するという表現技法(漢詩の押韻もそのようなものですね)があります。
ぜひ、みなさんも、「なぜ」「なぜ」と答えのない問いを積み重ねて、表現の工夫を読み取れるようになってくださいね。共通テストの問6を解けるようになれますように(^^♪