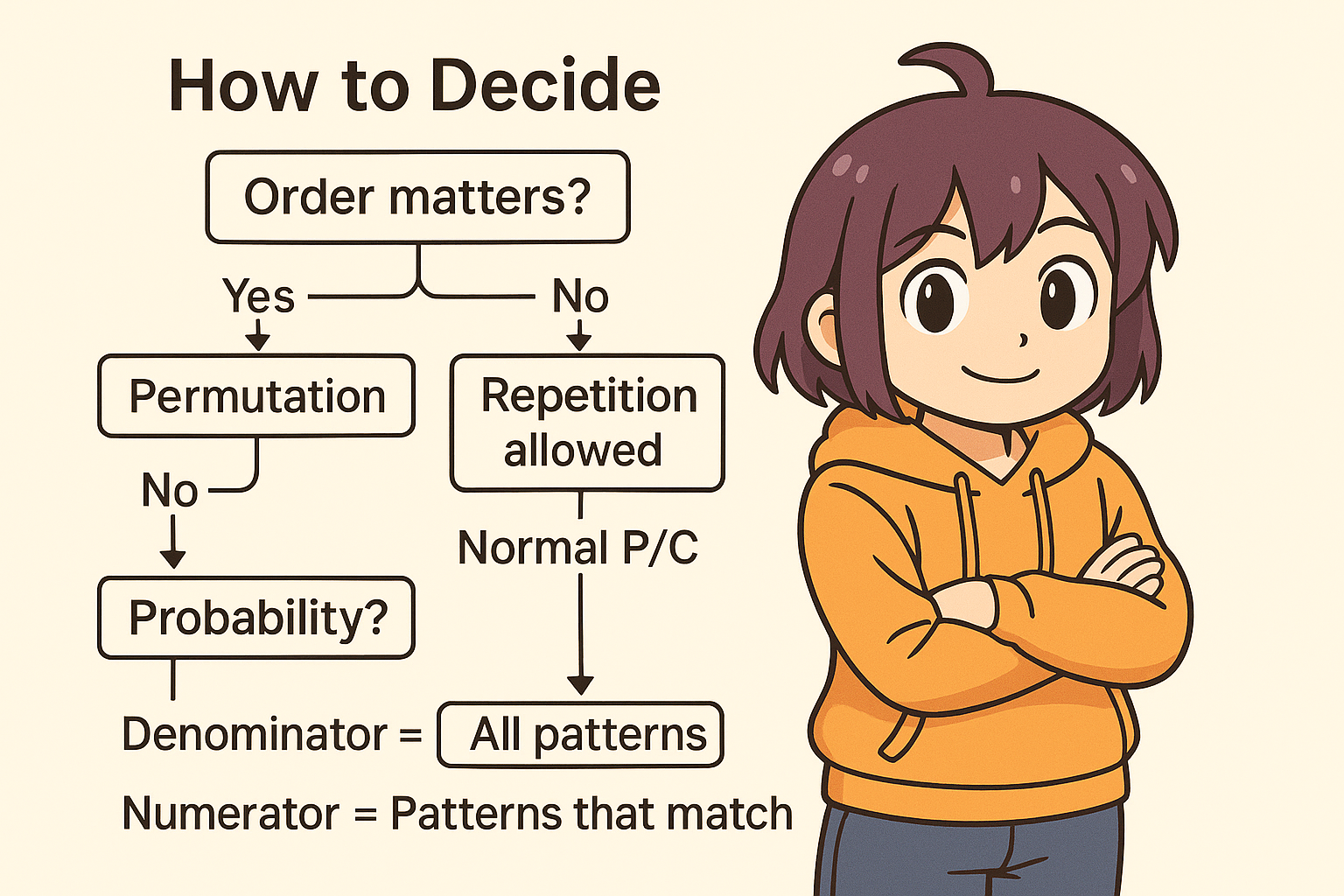確率の基礎判断法:問題文から「順列」「組合せ」を見抜くシンプル思考法【完全版】
1. はじめに
「確率の問題を読んでも、何を使えばいいかわからない…」
これは多くの高校生が抱える共通の悩みです。
特に、順列(P)と組合せ(C)、そしてそれらの重複版の使い分けで迷うケースは非常に多いです。
原因は「公式の暗記」に偏って、判断の順番や文章の読み取り方を練習していないこと。
この記事では、基礎の基礎からスタートし、どの条件を使えば良いのかを一発で見抜く方法を、例題・注意点・練習問題付きで解説します。
最後まで読めば、点で覚えていた知識が「線」でつながります。
2. 判断フロー
ステップ1:順番を気にするか?
◎ 順番が関係ある → 順列(P)
例:「並べる」「順位をつける」「順番を決める」「整列させる」など
◎ 順番が関係ない → 組合せ(C)
例:「選ぶ」「取り出す」「グループを作る」「チーム編成」など
ステップ2:同じものを使えるか?
◎ 同じものOK → 重複順列または重複組合せ
例:「同じカードを何回でも使える」「同じ数字も選べる」
◎ 同じものNG → 普通の順列・組合せ
ステップ3:確率かどうか
◎ 「…の確率」と聞かれている場合
1. 分母=全体のパターン数(順列または組合せで求める)
2. 分子=条件を満たすパターン数(同様に計算)
3. キーワード一覧
1️⃣順列(P)になりやすい言葉
◎ 並べる
◎ 順番を決める
◎ 順位をつける
◎ 列に並べる
◎ 座席を決める
2️⃣組合せ(C)になりやすい言葉
◎ 選ぶ
◎ グループを作る
◎ 抜き出す
◎ 取り出す
◎ チームを編成する
3️⃣重複ありのサイン
◎ 同じものを何回でも使える
◎ 同じ数字を選んでも良い
◎ 「元に戻す」「戻してもう一度」
4. 基礎例題
◎ 例題1
「5人から3人を選び、順番に並べる方法は何通りか」
→ 選ぶ+順番を決める → 順列
計算:5P3 = 5×4×3 = 60通り
◎ 例題2
「5人から3人を選ぶ方法は何通りか」
→ 選ぶだけ(順番なし) → 組合せ
計算:5C3 = (5×4×3) ÷ (3×2×1) = 10通り
◎ 例題3
「1〜6の数字から2個を選び、同じ数字もOK。順番は関係なし」
→ 同じ数字OK+順番なし → 重複組合せ
計算:(6+2-1)C2 = 7C2 = (7×6) ÷ (2×1) = 21通り
5. 間違えやすいパターン集
◎ 順番の有無を見落とす
◎ 重複の有無を見落とす
◎ 確率の分母を勘違いする
◎ 公式だけ覚えて文章を読まない
6. 練習問題+解答解説
◎ 問題1
8人から会長・副会長・会計を決める方法は何通りか。
【解説】役職が3つあり、順番がある → 順列
計算:8P3 = 8×7×6 = 336
【答え】336通り
◎ 問題2
8人から3人を選んでバレーボールのチームを作る方法は何通りか。
【解説】順番なし、同じ人を複数回選ばない → 組合せ
計算:8C3 = (8×7×6) ÷ (3×2×1) = 56
【答え】56通り
◎ 問題3
1〜5の数字から2個を選び、同じ数字もOKの場合は何通りか。
【解説】順番なし、同じ数字OK → 重複組合せ
計算:(5+2-1)C2 = 6C2 = (6×5) ÷ (2×1) = 15
【答え】15通り
◎ 問題4
1〜5の数字から2個を選んだとき、和が7になる確率は?
【解説】
1. 全体のパターン数:5C2 = (5×4) ÷ (2×1) = 10通り
2. 和が7になる組:(2,5), (3,4) → 2通り
3. 確率=2 ÷ 10 = 1/5
【答え】1/5
7. まとめ
◎ 「順番が関係ある?」→ Yesなら順列、Noなら組合せ
◎ 「同じもの使える?」→ Yesなら重複、Noなら普通のP/C
◎ 確率は「分母=全体」「分子=条件」で計算
◎ 動詞や条件をキーワードとして拾う習慣をつける