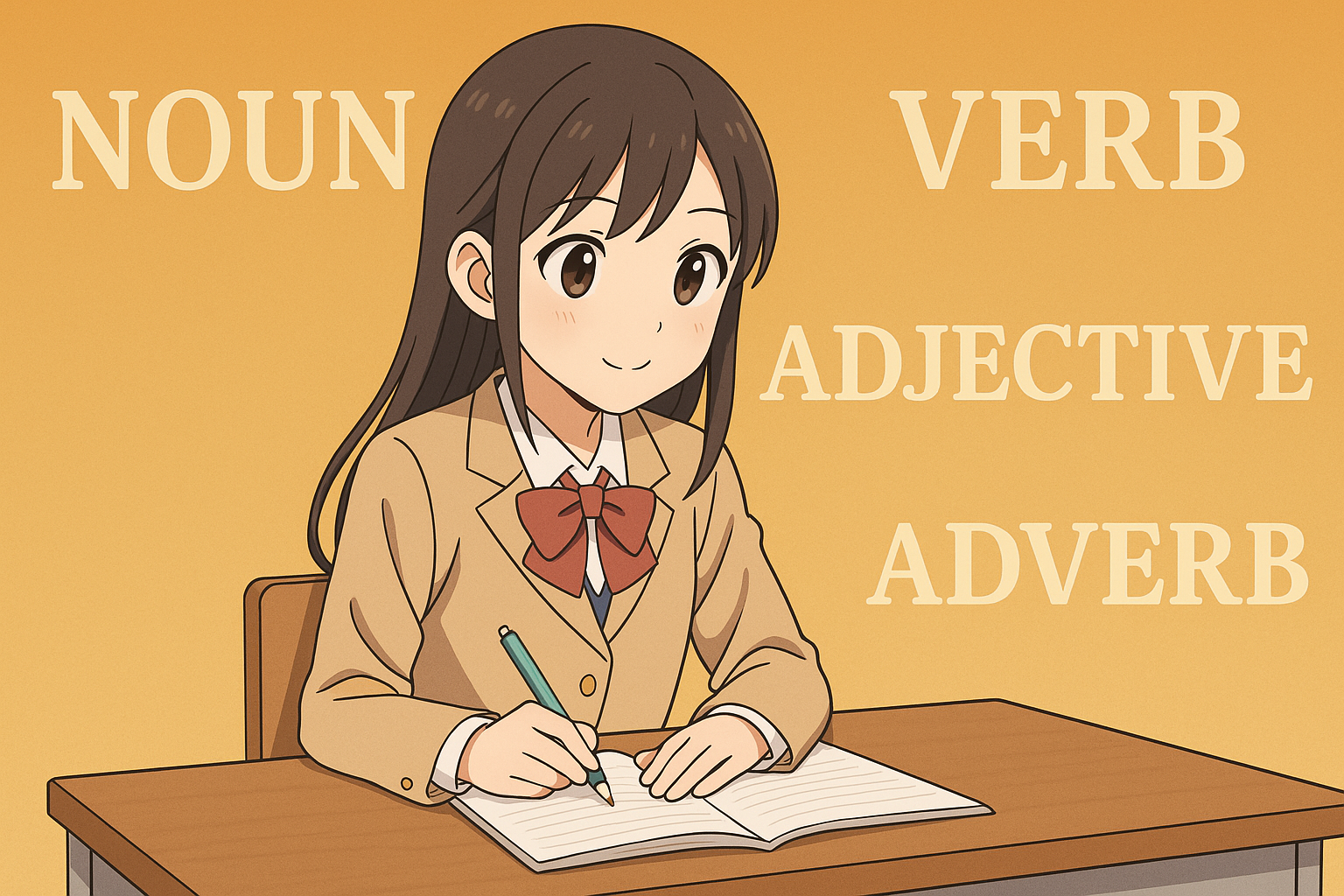学校の英語授業編第3回:じゃあどう自分で学ぶか(実践編)
📚 はじめに
これまでの記事でお伝えしてきたように、今の中学校の英語授業は「なんとなく英語」に陥りやすい傾向があります。また、公立と中高一貫の間には授業時間や構成の差があり、そのまま理解度や学力の差につながってしまう現実もあります。
では、そうした環境の中で 生徒が自分でできる工夫 はどんなものがあるのでしょうか。
今回は家庭教師として実際に指導してきた経験をもとに、「具体的な勉強の仕方」をお伝えします。
✏️ 1. 品詞の整理
中学生にとって、最初の大きな壁は 「品詞」 です。特に形容詞と副詞の違いが分かりづらく、多くの生徒が混乱します。
結論だけ言えばシンプルです。
◉ 名詞を修飾するのが形容詞
◉ 名詞以外を修飾するのが副詞
ただ、英語が苦手な生徒にとっては「なぜ日本語の文法みたいなことをやらなきゃいけないの?」と疑問に感じる場面も多いのです。
そこで僕は、まず 身近な日本語の例文 を使って品詞の役割を説明するようにしています。例えば「赤いリンゴを食べる」なら「赤い」が形容詞、「ゆっくり食べる」なら「ゆっくり」が副詞。このように実感できる形で示すと、ぐっと理解しやすくなります。
さらに、拒否反応が強い場合はあえて「形容詞」「副詞」という言葉を出さずに、文の構造を示しながら「ここに来る言葉はこういう役割だよ」と伝えることもあります。名前よりも役割を理解させることを優先するのです。
📐 2. 文型の理解
英語の文章は原則として 5文型しかない。
この一言を伝えると、生徒は「え、たった5種類?」と驚き、ぐっと興味を持ってくれます。
もちろん「目的語」「補語」といった用語が出てきますが、理解が早い生徒にはここで品詞の知識と結びつけて教えることで、文章の構造が一気に見えるようになります。
逆に英語が苦手な生徒には、まずは日本語の例文を用いて「主語+動詞」「主語+動詞+目的語」といったシンプルな形を示します。いきなり難しい専門用語で固めるのではなく、自分の生活に近い例で文型を体感させることを意識しています。
📖 3. 教科書の活用法
「教科書は一度読んで終わり」になってしまう生徒は多いですが、それでは力はつきません。そこで僕が提案しているのは、“分解”と“要約”のセット学習です。
具体的には次の4ステップです。
◉ ① とにかく一度読む(音読できるとベスト)
◉ ② 「なぜ?」を自分に問いかけながら読む(なぜこの単語?なぜこの語順?)
◉ ③ 赤字・太字の部分をピックアップし、その解説文までしっかり確認する
◉ ④ 読み終えたら、ページ全体の内容を自分の言葉で要約する(字数を決めてトレーニングすると効果的)
こうすると、ただの「暗記」ではなく 理解→整理→表現 までを一連でこなせるため、授業の知識が自分のものになります。
📒 4. ノート術との連動
英語には日本語と違う独自ルールが多いため、それをノートに「自分用のミニ辞典」として残すのがおすすめです。
例えば:
◉ 「三単現のs」や「時制の一致」など、日本語にはないルールをメモしておく
◉ 品詞ごとに色を分けて書く(名詞=青、動詞=赤など)
◉ ページ下に「今日のルールまとめ欄」を作り、授業のポイントを一言で書き残す
こうすることで、ただ写すだけのノートから 「見返すだけで理解がよみがえるノート」 に変わります。前回の記事で紹介した「ノートの再現性」ともつながる部分です。
🌟 5. 成功体験
このやり方を実践した生徒の中に、英語が大の苦手で「長文なんて絶対無理」と言っていた子がいました。
まずは「単語」と「文法」の基礎だけを徹底的に固めました。するとどうなったか。
それまで英文を見ても「単語の羅列」にしか思えなかったのが、ある日突然「文章の流れ」として見えるようになったのです。
その後は、リーディングや英作文の伸びがまるで違いました。文章を読むスピードも上がり、模試では以前より30点以上点数が伸びたこともあります。
英語が嫌いだったその子が、「文法が分かるとちょっと楽しい」と言ってくれたのは、僕にとっても印象的な瞬間でした。
📝 一言まとめ
英語の学び方は「丸暗記」ではなく、
品詞で整理 → 文型で骨格を掴む → 教科書を分解して要約 → ノートで独自ルールを整理 → 成功体験につなげる
という流れで初めて本物になります。
一つひとつは地味ですが、確実に積み重ねることで「なんとなく英語」から抜け出せるのです。