あなたは本当に“対比”を理解していますか…?
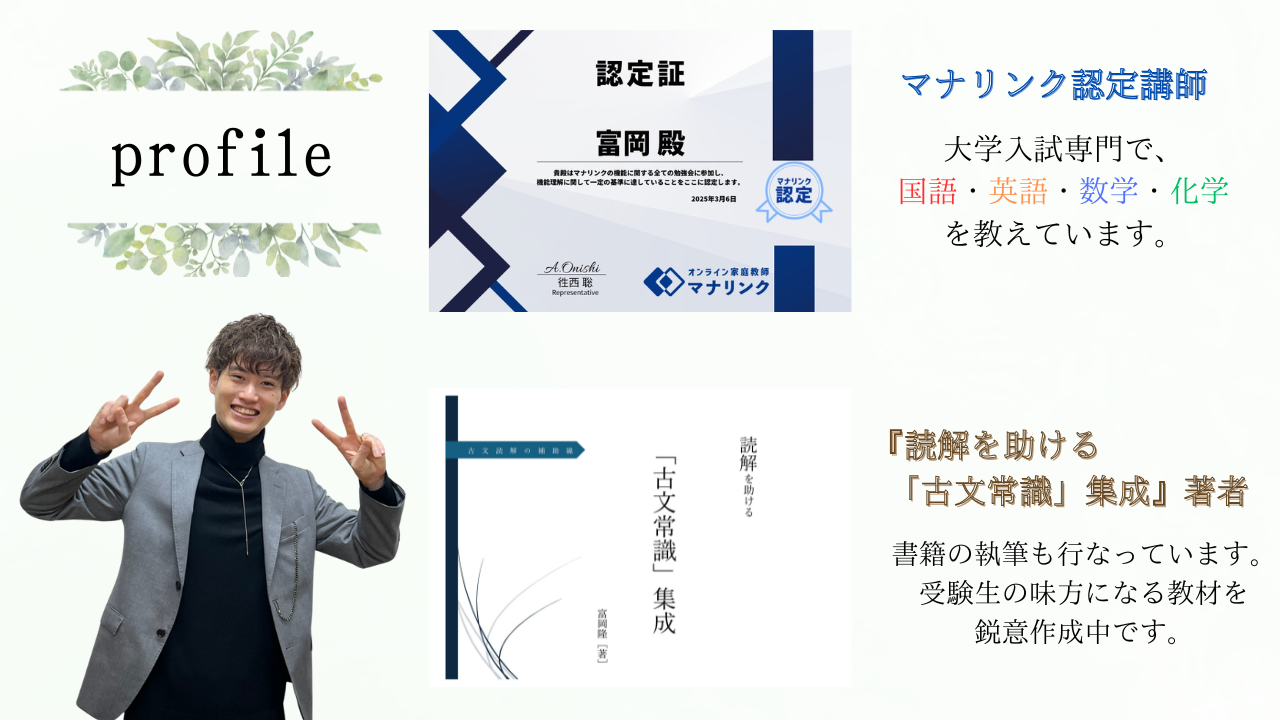
みなさんこんにちは!講師の富岡です◎
今回は、国語の中でも重要な“対比”について述べていきたいと思います。
ところでみなさん“対比”はご存知ですか?
「何だよ、そんなん知ってるよ〜」という人、本当ですか??
もし、次のように“対比”を捉えている人は、本当の意味での“対比”をご存知ないということです。
「対比は、AとBが反対。」
まあもちろん、間違っている、まではいきません。
ですが、次の3つの要素が考えられていますか?
①対比は共通を土台にしている。
②筆者はどちらに軸足を置いているのか。
③AとBよりも「AとAでない」の比較。
①対比は共通を土台にしている。
例を挙げてみましょう。
「このお店のカレーは、あのお店のカレーより辛い。」
当然対比されているのは「このお店」と「あのお店」ですよね。
ですが、この対比の土台には“共通”が潜んでいます。それは、
「カレーの辛さ」
という点です。
どういうことかというと、この対比は「カレーの辛さ」という点を土俵にして、「このお店」と「あのお店」が相撲をとっているイメージなのです。
このように対比するときには、共通の土台が必要です。
では、それがわかると何がオイシイのか。
それは、
「今、筆者は何をテーマにして話しているのかが掴める。」
ということです。
今回のような対比を見つけたら「あ、筆者は今“カレーの辛さ”をテーマにして述べているんだな」とわかるではないですか!
土台を見てあげれば、そこで話されている中心テーマが掴めるのです。
お分かりでしょうか?
みなさんは対比の表層しか見ていないのです。
まるで、綺麗な花ばかり見て、それを支えている土を見ないのと同じですよね。
対比を支える土台に注目できるようになれば、今何が中心のテーマになっているのかがわかるのです。
②筆者はどちらに軸足を置いているのか。
また、対比では、共通を土台としつつ、その土俵の上で相撲を取らせます。
ですが、筆者は多くの場合、そのどちらかの力士に肩入れしています。
例えば、筆者が日本建築の評論を書いている場合、
「西洋建築は左右対称性・幾何学性を重視しているのに対して、日本建築は左右非対称性、立体性を重視している。」
という文において、西洋建築と日本建築のどちらに肩入れしているかわかるはずです。
当然、「日本建築」に力点をおいて述べているはずです。
「西洋建築」は「日本建築」を述べるために“引き合い”として出されたものなのです。
天秤で考えてもわかりやすいですよ。
「西洋建築」と「日本建築」を天秤にかけたとき、筆者にとってどちらが重いのかを考えるわけです。
当然今回の場合は「日本建築」の方が重たくなりますよね。
さてそこで、みなさんにはすかさずこう考えて欲しいのです。
「じゃあなんで西洋建築をわざわざ引き合いに出したんだい?」
すると、以下の2点に気づきます。
A:共通の土台=中心テーマに気づかせたいから(①の話)
B:日本建築の話題だけでは理解されない恐れがあるから(③の話)
Aのパターンは先に見た通りです。
今回の例であれば、西洋建築を引き合いに出すことで、筆者は「建築様式」を共通の土台として(中心テーマとして)話していることがわかるのです。
一方、Bのパターンは③の話になるのでそちらに移ります。
③AとBよりも「AとAでない」の比較。
対比にはAとBという捉え方よりも、よっぽどAと「Aでない」の捉え方が良いことが多くあります。
数学では「Aでない」のことを余事象なんて言いますね。
それを考えるわけです。
今回の建築の例であれば、「西洋建築」というものは「左右対称性」「幾何学性」というものを持っているそうですが、「日本建築」については次のように言えそうじゃないですか?
日本建築は「左右対称ではない」「幾何学ではない」。
それを本文では「左右非対称性」「立体性」と述べているのです。
「左右非対称性」や「立体性」というのは、漢字がズラーっと並んでいるので、それだけで難しい!!と思いがちですが、だからこそ「左右対称ではない」「幾何学ではない」のように言い換えることが大切なのです。
もちろん、慣れてくればこれくらい、いちいち置き換えなくても理解できるようにはなってきます。
ですが、対比は「A」と「Aでない」によるものと捉えておくと、考えやすくなることが多いのです。
以上のように「対比」という読解の基本事項一つとっても、その意味は深く、自分のものにするのは容易ではありません。
対比構造を見かけたときに、これだけの頭の働かせ方ができる人とそうでない人とでは、読み取りに雲泥の差ができるのは当たり前ですよね。
こうして、国語の読解では徐々に徐々にライバルと差をつけていくことができるようになっていくわけですね。
何となく読みを脱して、常に高得点が取れる読みに移っていきましょう!