【理科】社会に出たら理科は不要?|子どもたちの理科離れについて思うこと
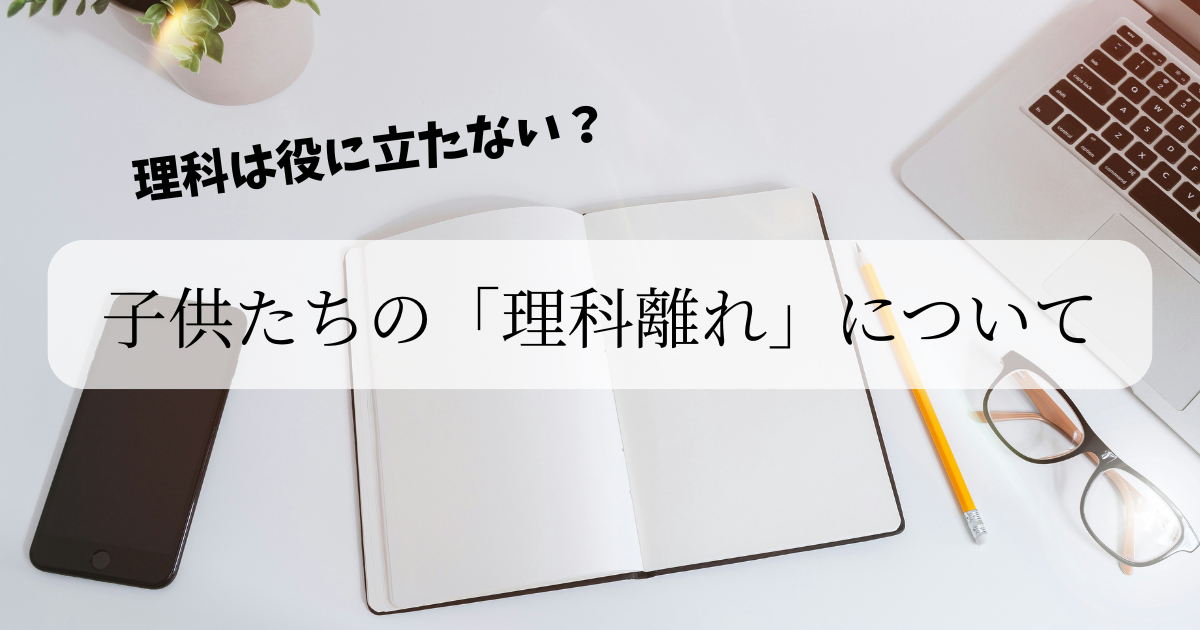
先日、こんな記事がSNSで話題になっていました。
「社会に出たら理科は不要」…日本の高校生が最多、日米中韓の4か国比較で「理科離れ」深刻
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20250703-OYT1T50224/
この記事によると、日米中韓の高校生を対象にした国際調査で、
「社会に出たら理科は不要だと思う」と答えた割合が、日本は4か国中もっとも高く、約46%にのぼったそうです。
アメリカ・中国・韓国では、「理科は役に立つ」と考える生徒が多数派を占めている一方で、
日本では「理科は実生活に関係ない」「覚えるだけで面白くない」といった理科離れの傾向が強く見られる、とのこと。
この結果に、驚きと同時に、どこか納得してしまった自分もいました。
なぜなら僕自身、家庭教師として理科を教える中で「理科って将来使わないでしょ?」「暗記ばかりでつまらない」といった声を、これまで何度も耳にしてきたからです。
でも、本当にそうでしょうか?
本当に理科は、「役に立たない」学問なのでしょうか?
理科が「つまらない」「役に立たない」と言われる3つの理由
① テストのための暗記で終わってしまう
理科と聞くと、多くの子がまず思い浮かべるのは「覚えることが多い」というイメージです。
化学式や用語、反応の名前など、覚えたはずのことがなぜかテストで出てこない。
そんな経験が、「理科=暗記科目」として子どもを遠ざけているのかもしれません。
しかも近年は、実験の機会も少なく、体感を伴わない授業が多くなっています。
「なぜこうなるのか?」を自分の中で確かめる経験ができていないのです。
② 日常生活との接点を感じられない
実は多くの子が「理科で習ったことが、生活の中にある」ことには気づいています。
でもそれが、「自分に必要だ」「自分に関係している」とは感じていない。
たとえば…
- 飲みかけのペットボトルを冷凍庫に入れて破裂させてしまった
- 台風前に頭が痛くなる
- スマホのバッテリーがすぐ減るようになった
これらすべて、理科で説明できる現象です。
でもそれを「へえ」で終わらせてしまえば、学びとはつながらない。
「知ろうとする姿勢」そのものが、失われていることが多いのです。
③ 「知っても仕方ない」と思い込んでいる
そして何よりも深刻なのが、「理科を知っても何にもならない」と子ども自身が信じていることです。
私は日々、理科が苦手な生徒さんと接する中で、
「たしかに理科で習ったことが身の回りにあるのはわかる。でも、それが自分の役に立つとは思えない」
という反応に出会います。
この言葉の背景にあるのは、強い無関心と自己防衛です。
無関心は「見えない拒絶」

「理科は身近にある」と伝えることには、限界があります。
目の前に現象があっても、それを見ようとしない。
わかろうとしないことで安心を得ている。
それは、知的な探究を拒む姿勢に近い。
私はこの無関心を、学びにおける最大の障壁だと思っています。
なぜならこれは、科学や教養を育てる大前提「知ろうとする意志」の放棄だからです。
理科が“生きた学び”になるために必要なこと
違和感や「なぜ?」からスタートする授業
理科は、現象そのものに子どもが興味を持っていなければ、知識として定着しません。
たとえばこんな問いかけをしてみると…
- 「シャワーからお湯が出るまでって、どうなってるか知ってる?」
- 「エアコンって、空気を冷やしてるんじゃないんだよ」
- 「冷蔵庫が冷えるって、どういうことか説明できる?」
これらはすべて理科の話です。
でも、最初に「理科の授業です」と構えてしまうと、子どもは警戒してしまいます。
大事なのは、「それって理科だったの!?」とあとから気づく体験を積ませること。
その驚きこそが、理科の世界に“自分から手を伸ばす”第一歩になります。
家庭教師だからこそできる、理科との「再接続」
対話から生まれる“気づき”の授業
学校の授業では、どうしても時間やカリキュラムの都合が優先されがちです。
けれど、家庭教師なら、子ども一人ひとりに合わせて雑談の中に学びを仕込むことができます。
理科が苦手な子ほど、
「こんなこと聞いても大丈夫かな?」
「またわからないって思われないかな…」
と不安を感じています。
だから私は、「わからない」を否定せず、むしろ「わかるって面白い!」に変える授業を心がけています。
理科の力とは、「世界の見え方を変える力」
理科とは、ただの知識の集まりではありません。
何気ない毎日の中に、「どうして?」と問いを持つ力。
知識によって、世界の解像度が上がる感覚。
それこそが、理科の本質です。
一度その視点を持つことができれば、
街を歩いていても、天気の変化にも、スマホの仕組みにも、
「知りたい」が自然と湧いてくるようになります。
まとめ
「理科がつまらない」と感じる前に、問いを持つ体験を
お子さんが「理科は役に立たない」と感じているとしたら、
それは勉強の仕方が間違っているわけでも、能力が足りないわけでもありません。
「理科と自分との間につながりを持つ経験」が、まだ足りないだけなのです。
私は、家庭教師として、そんな「つながる瞬間」をつくることを何より大切にしています。
知識ではなく、“知りたい”という気持ちに寄り添いながら、
理科が少しずつ“自分のもの”になっていくサポートをしています。
授業紹介
お子さまの「なんで?」を育てる家庭教師をお探しの方へ
- 理科の知識だけでなく、「見方・気づき方」を育てたい
- 無関心から一歩踏み出す“問いのある学び”を体験させたい
- 学校の勉強がつらく感じているお子さまに、前向きなきっかけをつくりたい
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回の体験授業では、お子さまの興味関心に寄り添いながら、
一緒に「理科ってちょっと面白いかも」と思える時間を過ごせたらと思っています。



